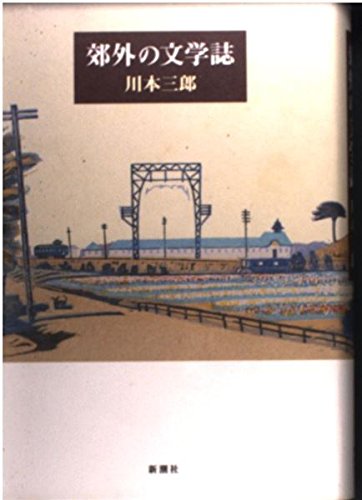『郊外の文学誌』川本三郎著を読む。
東京で暮らし始めて、驚くのは、文学者の生誕の地や終焉の地だのといった碑に出くわすのが多いことだ。えっ、こんな繁華街に住居を構えていた? 一瞬、そう思うのだが、渋谷だって百年ほど前までは、立派な郊外だった。
代々木生まれ、阿佐ヶ谷育ちの作者は自身の幼い頃の思い出を踏まえながら、東京の郊外の成り立ちを「文学」「文学者」という切り口で紹介していく。
「東京では刻々と風景が変わっていく。だから近過去へのノスタルジーという特別な感情が生まれてくる。京都や奈良のような古都に住んでいる人間は、東京の人間のように消えゆく近過去に対するノスタルジーを抱くことは少ないだろう」
作者のこの一文に、東京人の東京への思いが託されている。まあ、それは、ぼくのような東京に根づいてしまった地方出身者にもいえることなのだが。
田山花袋は、「落着いて創作活動をするため、(市中の牛込から)代々木の郊外に新居をつくったという」。山の手や下町出身の作家が、代々木あたりに越すだけで、なんか都落ちか、あるいは別荘感覚、いまならさしずめ、軽井沢とか伊豆高原あたりに家を建てる感覚だったのだろう。
いまや怪しげなエスニックタウンと化した大久保あたりも、昔は、寂しい新興住宅地だったとは。
徳富蘆花の住居跡は現在蘆花公園となり、現在も武蔵野の面影を留めているが、この雑木林はわざわざ蘆花が植林したものだという。
中野、阿佐ヶ谷、荻窪の郊外化による中央線文化の発祥の経緯も、好奇心をそそられる。井伏鱒二などの文士の街から、いっときは吉田拓郎に歌われ、フォークソングの街となり、パンクロッカーの街となって、いまにいたるが、高架となった中央線の電車の車窓からの家ばっかの眺めだけは、あんまり変わってないような気がする。
かつて『週刊新潮』の表紙の絵を描いていた谷内六郎の生家は、駒沢で牧場をしていたとか。あのノスタルジックあふれる絵は、谷内の幼い頃の駒沢界隈が原風景だったのだろうか。
東京の郊外化は西へ西へと拡大してきた。わかりやすい例でいうと、青山界隈(山の手)から渋谷、やがて田園調布、二子多摩川(新山の手)、多摩川を越えて、『金曜日の妻たちへ』でブレイクした横浜北部の高級住宅街(新々山の手)へ。
俗に「三代江戸に住んで江戸っ子になる」そうだが、いまの相続税制じゃあ、どだい、ムリな話。ハイカラな洋館や手入れの行き届いた日本庭園が、ある日突然、壊され、あとには、ミニ開発と称して、建蔽率ギリギリの隣の声まる聞こえの三階建ての家が建ってしまうようなんじゃね。
新しい郊外から、どんな文学がこれから生まれてくるんだろう。